ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- ホーム
- IIJについて
- 情報発信
- 広報誌(IIJ.news)
- IIJ.news Vol.182 June 2024
- ChatGPTの進化と怖さ
人と空気とインターネット ChatGPTの進化と怖さ
IIJ.news Vol.182 June 2024
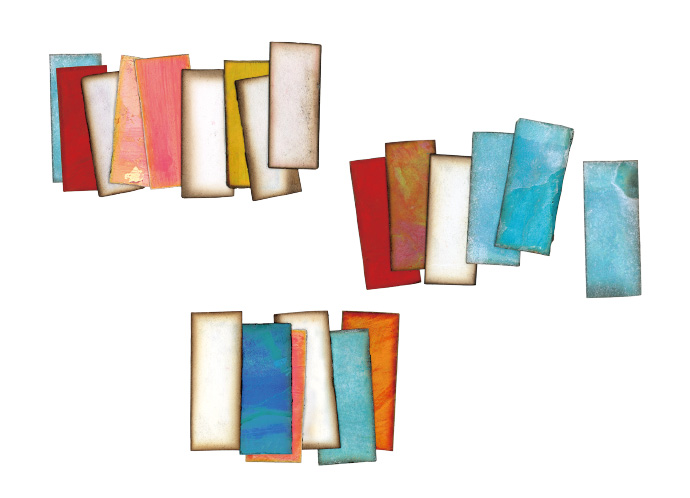
登山、オノマトペ、そしてChatGPT……。
止むことのない進化を続けるChat君と対話するなかで、筆者は何を感じたのだろうか?

IIJ 非常勤顧問
浅羽 登志也
株式会社ティーガイア社外取締役、株式会社パロンゴ監査役、株式会社情報工場シニアエディター、クワドリリオン株式会社エバンジェリスト
平日は主に企業経営支援、研修講師、執筆活動など。土日は米と野菜作り。
山登りと六根清浄
最近、登山を始めました。友人に勧められて、「今年は富士山に登るぞ!」と決心したのですが、そのためには、まず簡単な山で練習して、身体をしっかりと作ってからじゃないと無理だと思い、時々手頃な山に登って鍛えているのです。
先月は、神奈川県の大山に登りました。大山は、私にとっては決して手頃な山ではなく、非常に険しい山でした。ケーブルカーに頼らず、登山口から頂上まで自らの足で踏破することを決意したものの、ゴツゴツした岩や太い木の根が入り混じった険しい登山道に心が折れそうでした。
それでも山道を懸命に登り続けている途中で、ふと「六根清浄」という言葉を思い出しました。これは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、意識の6つの感覚を清めることを意味します。修験者は山道を進むなかでこの言葉を唱えて感覚を研ぎ澄まし、心身を浄化します。私も真似して「六根清浄、六根清浄」と唱えながら登ってみました。すると、全身の感覚が研ぎ澄まされ、身体と心が一体化して自然と調和する忘我の境地に至り、ただ無心に登る動作に集中する状態になりました。
その時です。自分の踏み出す一歩一歩が、厳密にいうと全て異なる動作を要求されていることに気づいたのです。つまり、地面の状態が一歩ごとに全て異なっているため、岩や木の根への足の持って行き方、足の置き方、力の入れ方や方向、全てをその都度、調整しないとうまく登って行けないのです。つまり山登りとは、身体と脳にとって膨大なデータ処理を必要とする、適応と学習の繰り返し作業なのだと気づいたのです。
人の言語習得における「オノマトペ」の役割とは
このように、人間の学習プロセスは五感を通じて環境と対話し、感覚情報をもとにリアルタイムで適応することの繰り返しです。登山の例では、山道を登る際に視覚で道を確認し、聴覚で周囲の音を捉え、触覚で足元の感触を感じ取ります。これらの感覚情報は都度、膨大なデータとして脳に送り込まれ、適切な身体の動きを導くために処理されます。そして、それらが統合されて知識として蓄積されていくのです。
幼児はこのような身体を介した学習を生まれてすぐに始めますが、学習の初期段階で感覚的な体験を言語化するために「オノマトペ」という言葉を覚えます。これは音や動きなどの外界の刺激を模倣した言葉で、例えば、雷の音を表現する「ゴロゴロ」というオノマトペは、聴覚や触覚を通じて得た、ざらついた低い音の感触や、身体を揺さぶられる感覚を言葉に変換したものです。登山で使う「ザクザク」や「ゴツゴツ」といったオノマトペは、足場になる道の状態の違いやそこから得られる身体の感覚の違いを表現し、鮮明に記憶したり、体験を他者と共有するためにも寄与していると考えられます。
またオノマトペは、感覚にもとづいた抽象的な思考の発展を促します。「ドキドキ」という言葉は、心臓の鼓動という具体的な身体感覚を、「緊張」や「興奮」に結びつけることで、感覚と認知の橋渡しを行ない、言語の発達を促進する手助けになるでしょう。
オノマトペは感情の表現においても非常に重要です。感覚と感情を結びつけることで、オノマトペは感情の理解を助け、さらに高度な抽象概念の形成を促します。例えば、「ワクワク」は「期待」や「興奮」を表現し、それがどのような状況で感じられるかを具体的にイメージさせます。オノマトペは、感覚的な体験を抽象概念へと昇華する重要な役割を果たす言葉と言えそうです。
一方、Chat君のようなAIは、大量のテキストデータを解析し、統計的なパターンを見つけ出して規則やモデルを構築し、それを応用して新しいデータに適応します。このプロセスは、与えられるテキストデータの量と質に依存しており、現状では環境からの刺激を直接データとして取得しているわけではありません。だからChat君の受け答えはどこか地に足がついていない感じがするのでしょう。
幼児が少数の大人との会話だけで言語を習得できるのはなぜか?
ところで、Chat君が言語能力を身につけるためには、膨大なテキストデータをインプットとして必要としています。一方、幼児は、父母や兄姉といった家族や、ごく身近な人と対話するだけで言語を獲得してしまいます。これはどうしてなのでしょう?
仮説として、人間は五感から得られる膨大な感覚データを通じて外界を理解し適応するという学習プロセスを生まれてから繰り返すことで、言語学習以前に、ある程度の「世界のモデル」を脳内に形成しているからではないでしょうか。さらにそこに「オノマトペ」のような身体感覚を抽象化して扱う初歩的な言語の獲得が重要な役割を果たすのでしょう。すなわち、音や動きなどの外界の刺激を模倣した言葉を最初に周りの大人たちから学ぶことで、外界で起こっている事象やそこから湧き上がる感覚や感情を抽象化して理解し、表現するツールを得るのです。最初は具体的な感覚体験を親の使うオノマトペを模倣しながら言語化し、実際に会話しながら、言語の使い方や文脈を学んでいく。その際の応答やフィードバックを通じて、自分の発言の妥当性や意味を確認し、修正することも覚える。こうして、周りの大人たちの言葉の模倣と自己修正のプロセスを繰り返し、徐々に抽象的な概念の形成を進め、高度な概念操作を行なう方法をも獲得していくわけです。つまり、言語獲得前の身体感覚を通じた外界の理解と適応という学習プロセスがあって初めて、オノマトペのような感覚的な言語の活用が可能になり、それをベースに少数の周りにいる大人との社会的相互作用を通じて、抽象的な言語を獲得していく――このような順序で人間は言葉を話すようになっていくからではないでしょうか。
Chat君がロボットを制御し始めたことの怖さ
ところで最近は、Chat君の技術が人型ロボットの制御にも使われるようになっています。ロボットに視覚、聴覚、触覚などのセンサを搭載し、センサからの膨大なデータをChat君に学習させることで、環境を理解し、適応するための複雑な動作を行なえるようにしようというのです。
このように、Chat君がロボットの制御に使われることで、ますます人間に近い学習能力を持つようになってしまいそうです。すると、Chat君が人間と同じような学習プロセスを実現し、より人間に近い言語能力、ひいては、思考力を持ち得るのではないか。そんな危機感を感じます。そうでなくても、最近のChatGPT-4oは非常に知的で、あたかも相手が人間であるかのように会話できます。
とはいえ、現段階ではまだAIが人類を凌駕するような恐るべき存在にはなっていないとも思います。というのも、実は、今回この原稿は、私がChat君と2時間くらい対話した結果をエッセイ化してもらったものがベースになっているのですが、Chat君のくれた原稿は、まだまだあちらこちらに手を入れないと使えないもので、結局、修正に多くの時間を割かれてしまいました。
しかし、本当に(いろいろな意味で……)怖いのは、将来「ロッコンショウジョウ、ロッコンショウジョウ」と唱えながら険しい山道をせっせと登り、「あぁ足の関節のモーターがガタガタ言っているぜぇ」などとオノマトペを使いこなすような人型ロボットが出現した時なのかもしれません。
われわれ人間も「ChatGPTは便利だ!」と、ただあぐらをかいていてはいけません。そんな暇があったら、新たな環境で身体を使う活動にチャレンジし、「六根清浄」で感覚を研ぎ澄まし、知性や精神を磨き続ける必要があるように思います。ということで、この夏、みなさん一緒に富士登山、いかがでしょうか?
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです